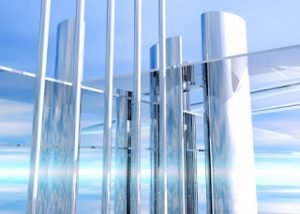運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)

最初の御相談から最終の契約書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います!!
エンジニア、デザイナー、コンサルタント、クリエイター等を
対象としたフリーランス向け契約書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)

予防法務としての契約書作成
<契約書作成の意義及び重要性>
日本法では、一部のものを除き、原則として、契約書を作成しなくても、当事者間の合意だけで契約が成立するため、現実社会では、契約書を作成しないまま、取引をしている場合が多いと思います。
特に、親しい間柄だとわざわざ書面にして合意内容を文面化するのは煩わしいというのが本音ではないかと思います。
もっとも、合意内容を文面化すると、以下のメリットを享受することができますので、手間がかかるとしても、きちんと契約書を用意するのが望ましいといえます。
①文面化することにより、ビジネス環境に即した特約の活用が促進されます。
⇒契約書に、強行法規に反しない限り、事業活動の実態に即した様々な条項を置くことができます。
例えば、無催告で解除できるようにする条項、相殺の決済機能を活かした相殺条項等が挙げられます。
②紛争性が帯び、裁判になった場合、契約書が証拠として残ります。
⇒裁判では、証拠により事実を認定するという方法で行われますので、契約書が重要な役割を担います。
ただ、どんな契約書でもよいというわけではなく、第三者にとって契約条項が明確な契約書を作成する必要があります。

フリーランスにとって無視できない契約書
受注した案件に関してフリーランスの方に起こりえるトラブルとしては、下記のような事態があり得ます。
(1)クライアントから提示される契約書において、報酬、契約解除等の事項に関し、フリーランスの方にとって不利な条項があるケース
(2)口頭で案件の発注を受け、実際に動いていたが、後日急にキャンセルになってしまったケース

上記の(1)の場合、契約書という書面があるため、クライアントとフリーランスとの間の契約の成否が問題となる可能性は低いですが、トラブルになった際、原則、契約書に記載された条項により、報酬請求の可否、解除の成否等が判断されるため、フリーランスにとっては、その契約書の内容を精査する必要があります。
上記の(2)の場合、契約書がなく、そもそも案件が成立していたのかが問題になり得ると考えられます。契約書がなければ、メール等の客観的な証拠が無い限り、「案件が成立していない。」=「契約が存在していない。」ということになり、フリーランスは、クライアントに対し、報酬を請求できない可能性が高まります。
いながわ行政書士総合法務事務所では、このような事態に対し、契約書作成又は契約書チェックを通じて、適切に対応いたします。

サラリーマンではないフリーランス
フリーランスは、サラリーマンと異なり、業務に必要なものはすべて自己で用意しなけれならず、クライアントから受領した報酬をそのまま自由に使えるというわけではありません。
受領した報酬からあらゆる経費を差し引いた後、自由に使えるお金が残る形になります。特にクライアントとフリーランスとの間の契約は、雇用契約ではなく、労働基準法等の労働者保護の各種法令により保護されないのが原則です。
(フリーランスの場合、最低賃金の保障といった概念がありません。)
そのため、実質的にはサラリーマンと比べて手元に残る金銭が減少することは頻繁にあり、これを防ぐため、経費を差し引いたとしてもそれなりの金銭が残るよう、報酬に関する条項については、余裕をもってクライアントと交渉し、かつ、慎重に対応するのが望ましいといえます。
もし、クライアントへ契約書のたたき台を先行して提示できるのであれば、自ら積極的に提示すべきといえます。

フリーランス保護法によるフリーランスの定義
フリーランス保護法によるフリーランス(フリーランス保護法上の正式名称=特定受託事業者)とは、次のいずれかのものをいい、代表者が1人で従業員を使用していない法人もフリーランス保護法上のフリーランスに該当する点に注意を要します。
(1)個人であって、従業員を使用しないもの
(2)法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

3条通知~業務委託契約の場合
「明示する内容」
フリーランス保護法が適用される業務委託契約において、クライアントは、フリーランスに対し、発注書、契約書その他形式の如何を問わず次に掲げる事項(=取引条件)を書面又は電磁的方法(電子メール、SMS、SNSのメッセージ、チャットツール等)により明示しなければなりません(=3条通知)。
(1)クライアント及びフリーランスの商号、氏名又は名称
(2)業務委託をした日
(3)フリーランスによる給付又は提供される役務の内容
(4)フリーランスによる給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日(期間を定めるものにあっては、その期間)
(5)フリーランスによる給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所
(6)フリーランスによる給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
(7)報酬の額及び支払期日
(8)報酬の支払方法(現金以外の方法で報酬を支払う場合)
なお、上記の事項のうち、その内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとされます。
この場合、クライアントは、フリーランスに対し、業務委託時に次に掲げる事項(=当初の明示)を明示をする必要があります。
(1)未定事項以外の明示事項
(2)未定事項の内容が定められない理由
(3)未定事項の内容を定めることとなる予定期日
もし、未定事項の内容が定められたときは、クライアントは、直ちに、次に掲げる事項を書面又は電磁的方法によりフリーランスに対して明示しなければなりません。
(1)確定した事項
(2)当初の明示との関連性を示す記載(ex.「この書面による通知は、〇年〇月〇日付け発注書の記載事項を補充するものです。」といった記載)
「電磁的方法による明示」
取引条件を電磁的方法により明示した場合、フリーランスから書面の交付を求められたときは、クライアントは、遅滞なく、フリーランスに対して書面を交付する必要があります。
ただし、次に掲げる場合には、フリーランスの保護に支障を生ずることがないため、必ずしも書面を交付する必要はありません。
(1)フリーランスからの電磁的方法による提供の求めに応じて、明示をした場合
(2)業務委託が、契約の締結も含め、インターネットのみを利用するものであり、クライアントにより作成された定型約款がインターネットを利用してフリーランスが閲覧することができる状態に置かれている場合
(3)既に書面の交付をしている場合

報酬の定め方~業務委託契約の場合
クライアントとフリーランス間で業務委託契約が締結される場合の報酬の定め方として、下記のものが考えられます。
(1)定額制
月額で定額の報酬額を定める方法
(2)タイムチャージ制
業務実施時間×単価で報酬額を定める方法
(3)成功報酬制
業務の成果により報酬額を定める方法

支払期日~業務委託契約の場合
「支払期日の規制」
フリーランス保護法が適用される業務委託契約における報酬の支払期日については、次のような規制を受けます。
1.原則
⇒クライアントがフリーランスによる給付の内容について検査をするか否かを問わず、そのクライアントがフリーランスによる給付を受領した日又はフリーランスから役務の提供を受けた日から起算して60日以内
2.例外1
⇒他の事業者(=元委託者)から業務委託を受けたクライアントが、その業務委託に係る業務(=元委託業務)の全部又は一部についてフリーランスに再委託した場合において、クライアントがフリーランスに対して次の事項を明示したときは、元委託業務に係る対価の支払期日から起算して30日以内
(1)再委託である旨
(2)元委託者の氏名又は名称
(3)元委託業務の対価の支払期日
(趣旨)
クライアントが元委託者から支払を受けていないにもかかわらず、再委託先のフリーランスに報酬を支払わなければならないとすれば、事業経営上大きな負担を生ずることになるため、このような例外が認められています。
3.例外2
⇒準委任型の業務委託契約の場合において、個々の役務が連続して提供される役務であって、次の(1)から(3)までの全ての要件を満たすときは、月単位で設定された締切対象期間の末日(個々の役務が連続して提供される期間が1か月未満の役務の提供委託の場合には、その期間の末日)にその役務が提供されたものとして取り扱い、その日から起算して60日(2か月)以内にクライアントがフリーランスに対して報酬を支払うことが認められます。
(1)報酬の支払について、クライアントとフリーランスとの間の協議により、月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供した役務に対して行われることがあらかじめ合意され、クライアントがその旨を明確にフリーランスに対して通知していること。
(2)クライアントがフリーランスに対してその期間の報酬の額又は報酬の具体的な金額を定めることとなる算定方式(役務の種類及び量当たりの単価があらかじめ定められている場合に限る。)を明確に通知していること。
(3) フリーランスが連続して提供する役務が同種のものであること。
「支払期日の特定」
フリーランス保護法では、次のような形で支払期日を特定する必要があります。
(正しい記載)
〇月〇日支払
毎月〇日締切/翌月〇日支払
(認められない記載)
〇月〇日まで
〇日以内
⇒「まで」又は「以内」という記載では、いつが支払期日なのか具体的な日を特定できないため、支払期日を定めているとは認められないことによります。

知的財産権の譲渡又はその実施等の許諾がある場合~業務委託契約
業務委託契約において、フリーランスからクライアントに対して知的財産権を譲渡し、又はその実施等の許諾が行われることがありますが、フリーランス保護法のガイドラインでは、その譲渡又は許諾の対価を報酬に加える必要があるとされます。

案件の解約~業務委託契約の場合
エンジニア、デザイナー、コンサルタント等のフリーランスが受注した契約を解約しようとする場合、まずは、契約書の内容を確認することになります。
その中に、中途解約の条項があれば、それをもとに中途解約の成否が判断されることになります。
一方、その中に中途解約の条項が定められていないときは、民法その他の法令により判断されることになります。
例えば、クライアントとフリーランス間の契約がいわゆる「業務委託契約」であり、その契約書の中に中途解約に関する条項がない場合、下記のように取り扱われます。
【業務委託契約が「準委任型」である場合】
業務委託契約が「準委任型」である場合、民法の準委任契約の規定を参照することになります。民法では、準委任契約をいつでも解約できる旨が定められているため、フリーランスは、原則いつでもその契約を解約することができます。
【業務委託契約が「請負型」である場合】
業務委託契約が「請負型」である場合、民法の請負契約の規定を参照することになります。民法では、クライアントは、フリーランスに生じた損害を賠償すればいつでも解約できるものの、フリーランスから解約することは、原則としてできないとされています。
上記のように、契約書に中途解約の規定がないときは、民法により判断されるため、中途解約に関し、希望する取り扱いがあるのであれば、その内容を契約書に定めることが重要となります。
なお、フリーランス保護法により、契約の有効期間が6か月以上の業務委託契約において、クライアントから中途解約を行う場合、クライアントは、フリーランスに対し、30日以上の予告を行う必要があります。

業務内容を定めることの重要性~業務委託契約の場合
「フリーランス保護法に基づく義務」
クライアントとフリーランス間の契約が「業務委託契約」の場合、それが「準委任型」であろうと「請負型」であろうと、フリーランス保護法に基づき業務内容を規定する必要があります。
また、業務内容を明確に定めないと「その業務は、委託した業務のはずだ。いや、それは受託した業務の範疇に入らない。」等の齟齬がクライアントとフリーランス間に生じてしまうことがあります。
「定め方」
業務内容の定め方については、次のようになります。
(1)業務委託契約を用いる場合
⇒業務委託契約に業務内容を規定し、又は別途クライアントからフリーランスに対して書面又は電磁的方法により業務内容を通知する。
(2)業務委託基本契約及び業務委託個別契約を用いる場合
⇒業務委託基本契約又は業務委託個別契約のいずれかに業務内容を規定し、又は別途クライアントからフリーランスに対して書面又は電磁的方法により業務内容を通知する。

コスト割れ~業務委託契約の場合
業務委託契約において、フリーランスが負担する労務費、原材料価格その他の費用に対してクライアントから支払われる報酬の額が著しく低い場合(=コスト割れの場合)には、買いたたきに該当するものとして、フリーランス保護法に違反することになります。

指定品の購入強制~業務委託契約の場合
フリーランス保護法により、業務委託契約において、クライアントがフリーランスに対して業務の履行のために指定品(ex.資材)の購入を強制する場合には、次のいずれかの事由が必要となります。
(1)給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合
(2)その他正当な理由がある場合

契約書作成時に意識すべきこと
フリーランスの方が契約書作成時に意識すべきこととしては、下記のものが挙げられます。
<曖昧な表現にしない>
契約書作成時に何よりも意識すべきことは、作成する条項について曖昧又は不明確な表現にしないことです。契約書作成の主要目的は、紛争予防にある以上、裁判官等第三者が見て、分かりやすいものにする必要があります。
<リスクの想定>
紛争予防の観点からは、契約相手を分析した上で、将来起こり得るトラブルに対し、契約条項(ex.期限の利益喪失、相殺等)であらかじめ手当しておく必要があります。
<フリーランス保護法等の法令違反>
クライアントから提示される契約書については、フリーランス保護法等の法令に違反するような条項が記載されている場合があるため、子の点の確認が重要となります。

対応可能な契約書例
フリーランスの方がクライアントと契約を締結する場合の契約書の種類としては、「〇〇業務委託契約書」、「コンサルタント契約書(=コンサルティング契約書)」、「〇〇開発委託契約書」等が多いと考えられますが、当事務所では、これらに限られず、秘密保持契約書(NDA)、ライセンス契約書等フリーランスの方向けに様々な契約書を作成しております。

事務所案内
<事務所所在地>
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿1004号
いながわ行政書士総合法務事務所
(対応業務:契約書作成)
E-MAIL:inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp
URL:https://www.inagawayobouhoumu.net/
お問い合わせフォーム: https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/
LINE:
Chatwork:
<最寄り駅>
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩1分
都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分
JR「新宿駅」 徒歩10分
<営業時間>
原則として、年中無休。当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。
初回相談を御利用の方は、一度御連絡下さい。深夜の相談も都合がつけば可能です。

当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽に契約書作成<<<
・ 契約書に関する疑問又は質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
もし、契約書作成により本業に支障をきたして
いるのであれば、今すぐ御連絡下さい。
行政書士を契約書作成に関する
「かかりつけ医」として御活用下さい!!

上記の画像は、当事務所の面談風景です。
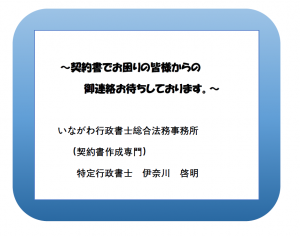
報酬
(契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費

契約書作成についての対応地域
<定型的な契約書から非定型的な契約書まで対応>
東京都23区内
足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区
東京都23区外
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村
神奈川県内
横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
埼玉県内
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町、宮代町、杉戸町、松伏町
千葉県内
千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、佐原市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、八日市場市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、八街市、印西市、沼南町、白井町
上記記載地域以外の場合でも、対応致しますので一度御連絡下さい。

お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
<お問い合わせフォームからもお問い合わせ可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
<LINEからもお問い合わせ可>
<Chatworkからもお問い合わせ可>
1:氏名(個人事業主又はフリーランスの方の場合、屋号及び個人名を明記)
2:住所
3:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
4:事実関係(経緯及び作成目的等を明記)
初回のお問い合せは、メール等によりお願い致します。お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。) 。
なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)

御依頼にあたっての注意点
<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(振込手数料は、御依頼者様負担。)。